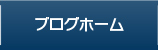TSI船着です。
最近よく質問を受けるのが、臨床試験で賠償保険に加入する場合、限度額はいくらが妥当か?というものです。
結論から申し上げると、試験の内容による・・・につきるのですが、実態は少し異なり、IRBの判断により決める場合があります。
つまり、がんのphaseⅡなどは、就業していない(出来ない)場合の被験者も少なくありません。一概には言えないのですが、賠償額の算出には「ライプニッツ」や「ホフマン」と言った係数が用いられます。
この二つとも、年収や、就業可能年数などを基礎にして「逸失利益」を算出し賠償額の目安を計算します。
つまり、非就業者は賠償額が低くなる傾向があるわけです。
そこで、依頼者から「賠償保険限度額」をいくらに設定すればよいか?という質問が来ると「〇〇ぐらいで良いのではないか」と案内します。しかし、IRBでは「少なすぎる」として3億円とか5億円の賠償限度額の保険契約をいただくことが少なくありません。
無駄ではないのかもしれません。ICFに「試験は賠償保険に加入している」というようなことが書かれていれば、被験者から限度額を確認されることもアリ、あまり少なければ理解を得られず被験者が集まらないような場合もあるからです。
問題は、IRBが理解の上進むものであれば良いのですが、イメージで保険金額を上げれば保険料コストも増えるわけで、プロジェクトの全体を考慮したスペックが必要だなぁ・・・と考えることも、時々あるわけです。
保険代理店の立場では僭越で言い出せない事実ですが・・・
よろしくお願いします。