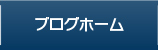お世話様です。
今日は治験保険をプランする中でちょっと困ることをご案内します。
賠償部分は特に問題が無いのですが「補償」に関して、けっこうあることです。
例えば「免疫抑制剤」等の試験、フェーズ2になりますと医法研ガイドラインでは、健康被害が起きた場合「医療費」「医療手当」をきちんとして責任を果たしましょう。という体で記載がされています。保険商品は「医法研ガイドライン」に準じて保険商品が設計されて、つまり、「ガンの患者向けの治験」は、医薬品副作用救済制度の対象にならない薬剤なので保険対象外。となる場合があるのです。
もちろん、厚生労働省で「抗がん剤の副作用による健康被害の救済制度について」議論がなされていて、一部「不公平」「趣旨から外れている」等の議論がされていることも承知しているのですが、毎度毎度で、保険業界は専門家が少ないためにこのあたりの変化についていけていない背景があることも問題であることを自認しております。
一方で、依頼者側も当局の見解と保険商品の乖離を認知できる機会は少ないために、コピペ(失敬)でプロトコルが作成されることも事実存在します。
ここで「問題の解決」は出来ませんので、頭を悩ませるわけですが、プロトコルに「この補償を担保する保険等に加入する」等とプロトコルにかかれてしまうと、保険業界側は引き受け可能な保険会社は限られますので、はたして良いことなのか…
これもまた悩ましい問題の一つです。
例えばCROがその点において「共有」出来ていればプロトコル作成時のアドバイスなどを行えるので、完成プロトコルがPMDA→施設IRBと進んだ際に保険のceitificateと合致しているので解決に近づくのですがいかがでしょうね?
さらに各保険会社と競争させることも可能ですので保険料コスト削減も期待できるかもしれません。
私はあと数年で引退しようと考えています。
残念なのは、臨床試験における被験者に対する賠償や補償と賠償保険商品の関連や問題につき完全に理解できる人にいまだにお目にかかったことがありません。
つまり後継者がいない訳です。
「できます!わかります!大丈夫です!」という方は多いのですがね…
まあ、今日はこの辺でやめておきます。
一緒に、創薬業界の賠償保険につき議論し理解し合い、ますます飛躍するライフサイエンス業界に、賠償保険というポイントから提案できるような仲間が出来ればありがたいなぁ… と、最近思うわけです。
株式会社TSI船着久稔 090-9003-7707 funatsuki@tmnf-tsi.co.jp
我こそはという方がいらっしゃればご連絡お待ちしています。
晴れやかな気持ちで引退したいんです!
TSI船着久稔