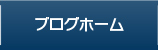ファームテックジャパン3月号に記事を書きました。保険代理店としては初めてとのことでしたが、私自身もはじめてのチャレンジでした。
書き始めると、いろいろな事例が浮かび、案外 スラスラ書くことができましたが、開発の方々が読む専門誌なので、保険と言う分野に関心が無い方がほとんどでしょう、出来る限り解りやすく書いたつもりですが…
弊社の社員に読んでもらったところ、「保険の部分は解るけど、臨床や非臨床については… 難しい保険ですね」と、言われてしまいました。
保険業界30年のベテラン社員ですが、ライフサイエンス業界と保険業界の両方を結び付けた理解はできていないとのことです。
まあ、そうでしょうね。保険会社の社員も不案内なことが多い、ライフサイエンス業界の賠償保険なのですから。
ところで、先日、厚労省の方とお話してきましたが、GCP14条の「保険等」で被験者への賠償と補償を担保するようにうたわれていますが、保険業界にライフサイエンス業界を理解する者が少なく、中には、健康被害が起こった際に補償できない保険に加入して臨床試験を行っているケースが散見される。という事実に驚いていました。
行政としては、「被験者保護をきちんとしなさい」「保険等を用いて」としていて、依頼者は「治験保険」に加入していることを原則としていて、施設のIRBには保険の付保証明を求められるし、PMDAへは「きちんと準備しています」として、臨床試験が始まるわけだが、前述の通り、保険として、被験者の健康被害を担保できていない実態が、たまに有るという話だ。
この場合、被験者への健康被害や訴訟に対する応訴を免れることは出ないから、依頼者は自社でその費用を負担しなければならず、役に立たない保険に加入していたということになる。
自動車保険に入っているつもりでいて、実は火災保険に入っていたようなイメージで、当然、自動車事故で保険金が出ない。というような感じです。
保険と言う物は、各社、大きな料率の差は無く、保険料に開きがある場合は「補償内容・補償範囲」が異なっていることが考えられます。その差が、明確でなければ、万が一頼れる保険か否か確認する必要がありますが、業界の言葉やプロセスを認知していないと、「それは範囲外です」等と言うことも起こるわけで、ライフサイエンス業界の要望に応えられていないということになるわけです。
保険代理店は、保険会社の作った商品を売る(対案する)わけで、一般的な保険の理解はお客さん以上に持っているのは当たり前ですが、特殊な保険は保険会社の社員でも理解できていないので、リスクにフォーカス出来ていない頓珍漢な保険契約になってしまう場合もあるわけです。