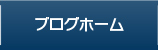おはようございます。船着 久稔です。
不明な方も多いのではないでしょうか。
先ずは「賠償」の保険金額ですが、保険商品の「1億円」「3億円」「5億円」というのはリミットです。よって、仮に死亡してしまった場合の賠償金は、収入や余命、就労可能年数など、ライプニッツ係数やホフマン係数を用いて算出されます。
試験によって、健常者や患者とありますから、本来は適正なものにするべきですが実態は「イメージ」で「1億より3億の方がいいだろ」というように決められています。
もっとも、保険料が3倍になったりするわけでもないので、それほど神経質になる必要もありませんが、オーバースペックにすることもないと思います。
補償は、国内試験ですと一般的なものは「医法研ガイドラインです」
イギリスのABPIガイドラインをモデルにしてある箇所もあるようです。
国内損保であれば「医法研ガイドラインの補償です」とプロトコルにあれば理解できます。
ただ、臨床研究の賠償保険は、役所からの要望もあり、「医療費」を担保できる場合もあるのですが、治験の場合は商品的に「医療費担保」の特約がありません。
患者さんの試験の場合は、「医法研ガイドライン」の「医薬品副作用被害救済制度に準ずる」とありますが、「医療費」の部分は依頼者=保険契約者が負担することになります。
※この部分は、整理しなければいけないのですが、施設のIRBで指摘されつつも、うやむやになる場合が多いです。
もっとも、医療費ですから何でもかんでも保険というより自己負担の方が正しい気もします。(IRBではそうならないことも存じています)
簡単に記しましたが、賠償は法律上負うもの。補償は依頼者と被験者のICF等による約束で「医法研ガイドライン」を参考にしている。その、医療費の部分は依頼者の負担であることを認識しておく。
この辺が重要だと思います。
ABPIガイドラインの件はまたお話ししますね