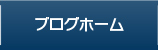九州大学に行ってきました。
第2回 TR推進合同フォーラム-動き始めたライフイノベーション- に参加するためです。
昨年に引き続き2回目の参加です。
なんで、保険関係の会社が???
と、思われるかもしれませんが、業界の情報を得て、適正な保険商品を提案するために欠かせないイベントの一つです。
今年は、ポスターも展示させていただきましたが、きっとみなさん、同じように「なんで保険・・・?」と思われたでしょうね。笑
内閣官房健康・医療戦略室 次長 菱山様、NIH国立トランスレーショナル科学先進センター mr Anton Simeonov 政策研究大学院大学准教授 隅蔵様 のお話を拝聴し、「我が国の考え方と取り組み」「アメリカでのTranslational Sciences」「ライフサイエンス分野の知的財産」について、知識を得ることができました。
日本には優れた「シーズ」が多くあり、国も産業として成り立つよう予算を設け、各国立大学は連携してサポートしネットワークを構築している。気になるところの知的財産はきちんと守られ、今後が楽しみになるお話を日本人の一人として誇らしく感じたものです。
日本は医薬品ベンチャーがもっともっと登場するべきです。
私自身も、本気で創薬ベンチャーを立ち上げようと考えていますが、九州大学を中心としたAROの仕組みは、一種のフィルターにもなると考えるので、投資する側も興味深いところです。
非臨床を終えて、安全性が確認され効果も期待できる「新薬開発」となれば、海のものとも山のものとも(失敬)つかない、被験物質に投資するより、少しはリスクが少なくなるでしょう。
例えば、ライセンスアウトされたシーズでphase1から行う。そのために企業を立ち上げる。投資側からも期待できる話だと思います。
ところで、私がベンチャー企業を立ち上げ、人を雇い、CROに依頼して臨床に入ったとします。
そこまでに、ライセンスフィーを除いて1億円かかったとしましょう。(人件費やその他経費です)
始まってみたら、「対象被験物質のデータに改ざんがあった。」「DMに過誤があった。」
そんなことで、経済損失を負ったら困っちゃいます。
投資はもちろん投資ですからゼロになることもありうると覚悟しています。
しかし、ステークホルダーに対する責任や、経費については黙っていられません。
アメリカでは、こんなときのために「保険」を使うのです。
E&O(Errors or Omissions Liability)いわゆる業務過誤により経済損失を与えた場合に「賠償金」を「保険金」で支払う。というもので、既に商慣習となっています。
日本では、「申し訳ありませんでした」で、済む話も海外では、「じゃあ保険で」となるわけです。
つまり、性悪説から言葉より「契約書」や「保険」をいざという時の担保にしているんですね。
海外との契約の場合注意点が2つあります。
①契約書で求められる保険は、何保険なのか
②訴訟時の管轄地はどこか。
今感じていることは、産学官が一体となって推し進めるライフサイエンスイノベーションは、商慣習や賠償リスクに変化をもたらす。
この理解で日本を他のアジア諸国と相違したグローバル化にきちんと対応できる国としていくことも、大切なことだと思います。