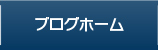3月に入ったというのにまだ寒い日が続きますね。とくに北海道地方は昨年のような痛ましい事故が起こらないことを祈ります。
さて、今日は医師主導型の臨床試験のことについて、どんな保険加入が適切なのかをご案内します。
ポイントは、①当局に製造承認を求める治験か②研究③昨今話題となっている「依頼」を受けたものか。この違いで加入するべき賠償保険が変わってきます。
①についてはGCP14条により被験者への賠償と補償を担保した「治験PL」保険に加入することが一般的です。②については「臨床研究用の賠償保険」に加入することになります。治験PL保険では担保されませんし、治療となるものは「医師賠償保険」で担保することになります。③は、いままで保険付保という考え方があまり適当でなかったのですが、施設(大学病院等)で行われる治験により被験者または第三者からの訴訟リスクや、賠償に備えるために施設自身が保険加入することが良いのかもしれません。
アメリカでは、治験を実施する施設は同様の施設を守る保険に加入しています。
なんか、最近の報道を見ると、日本も必要になってくるのかなと感じます。
TSIでは「ライフサイエンス賠償保険」で、プランすることになりますが、①②③ともに保険提案を行いますが、残念ですが、モラルリスクを保険で担保することはできません。
しかし、連日の報道を見ていると今後どのようになるのか… 不安であり興味深い?ところではあります。
先日、ある方の「たいした問題ではない」というブログに、コメントしましたが、数少ない新薬開発可能国である我が国が、これではだめだ… と感じました。
でも、昔からこうでしたよね。
だから、改めましょう。
国策として産業化しようとしているライフサイエンス業界です。「張り子の虎」のように思われないように、正々堂々と行きましょう!
万が一の賠償には、適切な保険で企業やステークホルダーを守りますから。
(宣伝)(笑)