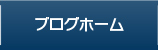おはようございます。船着です。
タイトルの質問が、たま~に来ます。
GCPや臨床研究法でも「保険等で」って書いてありますし、倫理的に考えておかなければならないけれど具体的にどうすれば…
まあ、大概の方はご存知とは思いますが、補償のガイドラインは「医法研ガイドライン」を用いることが多いようです。
健常人は「政府労災に準じ」患者は「医薬品副作用被害救済制度に準じ」というものがスタンダードです。
少し長くなるのですが、賠償は「法律上負うもの」補償は「依頼者と被験者の約束」と大まかに違いがあります。
※海外では考え方が違うので後日案内します。
保険商品では「賠償保険」の特約に「補償責任」を追加します。(一部の保険会社はインクルーズされていています)
いずれにしても、当局が、省令や法律で「被験者保護」を義務化していますが、どのように対応することがベストなのかは「依頼者や当事者で考えなさい」というのが厚労省の考えのようです。
保険商品は保険会社で考えなさい。とも言われました。
当たり前と言えば当たり前なのですが、当の保険会社も理解できていないことが多いようで、相談される保険契約に首をかしげることも少なくありません。
補償内容を充実させて、被験者にアピールして参加者を確保してスムーズにしたいということは誰でも考えますし望ましいことです。
だけど・・・ その補償担保は「保険商品」に頼ることを前提としているなら、保険商品の内容について事前に「担保できてるか」「担保できてないか」確認しておくべきですよね。
たまに、「このプロトコルとSOPで承認とったんだから、保険で持てない部分があるのは困る!」と怒られることがありますが、そうではないと思います。
理解の不十分なことほど怖いものですよね。
先日は、PMDAのホームページの「医薬品副作用被害救済制度」補償内容と「医法研ガイドライン」の「医薬品被害救済制度に準じて」は少し違うし、目的が異なる旨の案内をしました。
誰も説明してくれないから混乱しますよね。
本当はCROがその辺りも整理してくれるとありがたいと考えています。