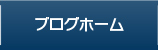おはようございます。TSI船着です。
海外試験が増えてきていますが、被験者確保とコストの関係でしょうか。
専門にしているCROも増えてきていますね。
さて、海外試験での「賠償と補償」ですが、ICHGCPの理念は世界不変ですので当然求められるものですが、もっぱら「賠償」部分がほとんどのようです。
肝心なのは、むしろICFで、副作用などネガティブな情報もきちんと書いてある方が、健康被害発生時のリスクが少なくなります。
日本は、皆保険制度があるので、あまりネガティブなことをICFに書くと被験者が集まらないという別の側面がありますが、外国では治験や臨床研究に期待する被験者側の気持ちが違うので、包み隠さず開示すればトラブルになることも少ないですし、起こったとしても正々堂々とした対応がやりやすい面があります。
賠償責任能力を持たずに健康被害を出した場合は、倫理に基づき追及されるようです。(保険加入しないでコストを優先させたなど)
オーストラリアの一部では、賠償保険加入は「強制」で、倫理委員会でも必ず確認されます。
この、倫理委員会が「施設」のものではなく、第三者機関なので容赦ないようです。
ちなみに、オーストラリアで試験を行う場合は賠償と補償(補償はABPIガイドライン)を求められることが大概です。
賠償保険の保険期間も倫理委員会から指摘されることもあり、往生したことがあります。
「試験期間」で問題ないものを、『サイトクローズまで保険期間延長とせよ。』という指摘です。ナンセンス!意味がない!
と、発言したのですが、倫理委員会は最後まで「見解」を変えませんでした。
保険に「不案内」なことが原因なのですが、オーストラリアのライフサイエンス事情を理解しないと、解決しないことだと思います。
最近は、同じようなことを現地(オーストラリア)からリクエストされても無抵抗。「はいわかりました」とお応えするようにしています。
よろしくお願いします。