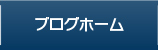おはようございます。TSI船着です。
今日は、そもそも論です。
実態として「健康被害が発生して賠償責任を負うこと」はたまにありますが、ほとんどが保険金請求をして解決することはないのです。
じゃあ、どうしているか?というと、依頼者が自己負担をして「示談」してしまう。
こういう解決が多いように感じます。
損害率(事故率)は低い分野ですので、保険料はもう少し安くても良いように思いますが、保険商品を作るのは保険会社ですので代理店が立ち入れない部分です。
保険加入は必要なのか?
これは、「絶対に必要」と言うものではありません。
GCPにも「保険等を用いて」という表現で、健康被害に対する賠償能力を担保するように書いてあります。
しかし、施設IRBでは、大概保険加入を確認され、入っていないと問題になるようです。
賠償能力とは、支払い能力ですから、依頼者の規模や試験の内容によるところもあると思いますが、保険加入を強く求められることがほとんどです。
CROは、クライアントに「経済損失賠償」を負うことがあります。
業務に過誤があり、試験をやり直さなければならなくなった。等が例ですが、こちらは今後、絶対に必要になると思います。
グローバル化すれば・・・と、案内してきましたが、国内のクライアントからも賠償請求されるようになりましたので検討が必要です。
話を戻して、GCP上の理念の定義が、IRBでは、責任の所在と担保になっているように思えます。
TSIがやることではないかもしれませんが、我が国の臨床試験やライフサイエンスの発展に、考え方の一致が必要な時期だと思うのです。
健康被害が発生した場合、お金で済む話でしょうか。
保険が賄えるのは、「金銭的」な部分だけです。
行政、依頼者、施設、CRO、保険会社。各社同じテーブルで話し合いを行いたい。と考えて、来年から動き始める準備中です。
よろしくお願いします。