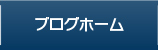みなさんこんにちは。
というのも、このブログも案外見ていただいている人がいらっしゃるということで(笑)赤面します。
本日は、国内保険会社が次々と商品開発した「再生医療賠償保険」について書きます。
結論から言うと… 「本当に業界現状」にmatchしているとは言い難いと思います。
被験者に対する健康被害の賠償と補償はGCP ICH-GCPに書かれているとおりで、業界では当たり前のことです。
もう一つ当たり前なのは、施設に対して「賠償と補償の体制ができている」との証拠の一つとして、保険付保が求められている。ということです。
国は「ガンのphaseⅡ以降に補償は必要ない」と言います。しかし、施設に「国がそう言っているので、補償はありません」という理屈が通用する場合と通用しない場合があるはずです。
つまり、保険会社の商品は、国の基準に合わせたもので、現場の事情に応える商品になっていないと言えます。
私見として再生医療は、健康被害リスクも訴訟リスクも一般薬の開発(臨床試験)に比較して低いと考えています。一種の治療に近いものもあるでしょう。
しかし依頼者が「厚労省が補償責任は無いと言っているので保険担保(補償部分)はしません。」とIRBで言い切り、理解を得られるとは思えないのです。
保険会社の考え方は、上記のケースで補償部分を担保する商品を開発すると、慣習が変わり、保険会社のリスクが増える。と言うものだと思います。(確かにその通りで、ある意味同感です)
問題は、保険商品が存在しないので補償部分については「依頼者で担保する」とIRBで説明し、ICにも同様のことを明記して被験者が集まるのだろうか?試験ができるのだろうか?という懸念です。(ガンの場合は集まるかもしれませんがね)
いずれにしても「治験」のハードルが保険商品で低くなり、業界が益々発展すれば良いなぁ。と、心から思うわけです。
ここからは、宣伝ですが(笑)TSIでは上記問題に対応する保険商品も取り扱っております。