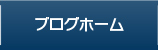久しぶりの更新です。
春から夏にかけて、仕事と遊びで夢中になっておりました。(笑)
再生医療の保険の引き受けですが、基本的に可能です。
治験であれば、治験PL。研究であれば、ライフサイエンス保険。治療であれば、医師賠償保険または、ライフサイエンス保険。
ただ、通常保険会社のに問合わせても、なかなか回答が来ないと思います。
そんなときは、TSIにお問い合わせください。
再生細胞の委託が可能になりましたが、こちらも保険があるのです。
たとえば・・・
委託先が預かった細胞を過失により「ダメ」にしてしまい、研究や試験に影響が出て「経済的な損失」が出た。モノを担保する保険。
どうでしょう?委託した先の「業務過誤」により、自社が負った経済損失は請求したいですね。
日本の商慣習では、代金を支払わない、再作成費用を払わない。という解決策が一般的ですが、「経済損失」を担保する保険に委託先が入っていてくれたら心強いですね。
お問い合わせは
03-3667-7770
TSI 船着(フナツキ)まで。
※自分自身も勉強していきたい分野です。