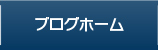おはようございます。船着です
自社の開発した「承認前」の被験物質を、例えば貸与して、貸与先が臨床試験を行う場合の保険の考え方について説明します。
貸与されて試験を行う施設、または責任医師は「臨床研究賠償保険」等の「被験者に対する健康被害」に対する保険付保を検討してください。
一方で「貸与側の企業等」は、基本的に賠償責任を負うことは少ないですが「医薬品PL」(承認前なので保険会社の承認が必要です)
または「ライフサイエンス賠償保険」に加入しておくと安心です。
リスクが全くないわけでもなく、備えておくと安心ですね。コストと相談して検討してください。
ちなみに、外国に「被験物質」の提供を行い、試験をする場合「提供元」も保険加入を求められることが多いです。
保険会社の社員に「承認前の被験物質」と「概要書」等の資料を出さずに「保険お引き受け」を依頼しても無理だと思います。
一般的な「PL保険」は承認後の医薬品を対象としています。未承認物質を別の者が使用して行う試験・・・
案外あるのですが、保険と薬、両方の知識で商品を組み立てないとダメなんですよ。