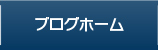保険代理店は保険会社が作ってくれた商品を販売することが主だった業務です。
しかし以前から「それだけでは不十分」と感じていて、ましてや「ライフサイエンス」といった専門分野では「保険の知識」だけでは「ダメだ!」と思っていました。
あるクライアントさんの役員の方から「社員にこういう保険に入っていて事故の際はどういう手順で対応するのかSOPみたいなものを作ってはどうか」と言う貴重なご意見を頂き(ビールを飲みながら)
「グッドアイディアだ!」と、クレーム対応SOPの作成を始めました。
これは絶対に必要なことだと思います。
①会社がどのような保険に入っているのか
②クレームが発生したらどんなことになるのか
③クレーム対応はどうする
④クレームを大きくしないためにどうする
⑤クレームに対し保険金請求をするにはどうする
いろいろな項目が浮かびます。
考えてみれば、保険契約時に実際に事故に対面する社員の方は「保険内容」や「保険加入」について「知らない」というのは、現場で混乱することになりますし、賠償事故で一番大切な「初期対応」のタイミングを逸することになるのでダメージが大きくなってしまうことも考えられます。
ちなみに賠償保険には「事故発生ベース」(事故が起こったときに保険期間であること)「損害賠償請求ベース」(賠償請求が起こったときに保険期間であること)「賠償請求報告ベース」(賠償事故が起こって報告するときに保険期間であること)と言うものがありますが、「報告ベース」が一番対応しやすいと自身では考えています。
保険代理店の仕事の範疇を越えるかもしれませんが「クレーム対応SOP」作成致します。
できる限り「簡単な言葉で」(笑)