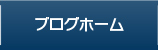こんにちは。TSI船着です。
本題にいきなり入りますが、弊社ではかなり以前から「守秘義務契約書」の締結にご対応しております。
NDAを保険会社、保険代理店に依頼をした際に「保険会社や代理店は守秘義務がありますので」と言われたことはありませんか?
その通りで、法律上も守秘義務を負っていることが事実です。
しかし、NDAは違う意味合いを持つ場合があります。
プロセスです。社内や関係先に、保険の見積もりを依頼した代理店にプロトコルを開示した。「NDAは?」「あ!結んでいません」「それはまずいじゃないか」というような、対外的なハレーションに対応するためです。
これは、業界理解の話かもしれませんが、ライフサイエンス専門保険代理店を標榜している弊社は、積極的とまでは言いませんが、事情を理解し柔軟に対応させていただきます。
よろしくお願いいたします。