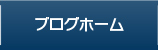おはようございます。TSI船着です。
同じ保険種目でも保険料が違いますよね。でも、あまりにかけ離れている場合は疑ってください。
基本的に保険料は、ほぼ各社同じ料率ですが、企業努力やきちんとした根拠により料率を変更することができます。
気を付けたいのが、「根拠要」で、単純に「他社より保険料を安くする」(値引き)することは出来ない決まりになっています。
医薬品PL保険を例にとりますと、基本的な料率があり、契約者から「根拠」を示す「質問書・申告書」または「事故防止に対するSOP」等がきちんとしていて、事故を起こす確率が低いと認められる。よって保険料率を下げる。ようなプロセスが必要になるのです。
仮にこのプロセスが無く「他社がいくらできているから…」という「値引き」は最悪「特別利益の提供」とみなされ、金融庁からお叱りを受け、適正な保険料を徴収しなさい。ということになります。
痺れるのが、その差額保険料は「契約者様」の負担となってしまうのです。
契約者は「保険会社が出してきた保険料なのだから」と、納得いただけないと思うのですが、ここは曲げられないルールです。
仮に、保険会社または代理店が差額分を負担しても「特別利益の提供」として処分されます。
保険会社も保険代理店も、金融庁監督下の仕事です。
ライフサイエンス業界同様に当局に厳しく指導される業界ですから、あまりかけ離れた保険料差は根拠を示しているか否か確認して検討するようにお願いします。
宜しくお願い致します。